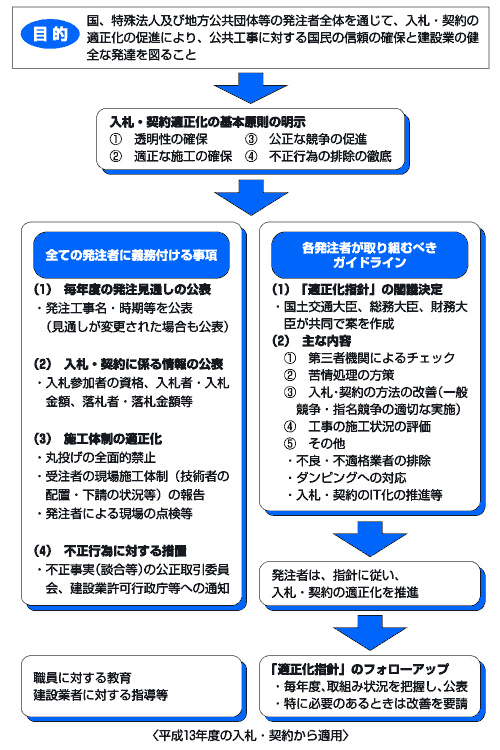| 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律のあらまし | 平成13年2月 |
| 第2 適正化法の主な内容 |
| 1 適正化法の概要 適正化法の概要は、下記の通りです(図−参照)。 |
| 適正化法の概要 | |
|
| 2 適正化法の主な内容 (1) 適正化法の対象工事 | ||||||||||
|
| (2) 入札・契約の適正化の基本となるべき事項 公共工事の入札・契約は、次の事項を基本とし、適正化を図るものとしています。 ○ 入札・契約の過程、内容の透明性の確保 ○ 入札参加者の公正な競争の促進 ○ 談合その他の不正行為の排除の徹底 ○ 公共工事の適正な施工の確保 |
| (3) 全ての発注者に対する義務付け措置 a)毎年度の発注見通しの公表 発注者は、毎年度、発注見通し(発注工事名、入札・契約の方法、入札予定時期等)を公表しなければならないものとしています。例えば年2回程度、年度当初には年度全体の見通しを、下半期初めには年度後半の見通しを公表する、といったことが考えられます。なお、災害直後に緊急的に行う復旧工事や用地の取得や関係機関との調整が終了していない等の理由により、公表時点では発注の見通しが立っていない工事は、公表の対象から除かれることとなります。 さらに、国、特殊法人等及び地方公共団体の行為を秘密にする必要がある場合や、予定価格が少額である場合は、対象から除外することとしています。 b)入札・契約に係る情報の公表 発注者は、入札・契約の過程(入札参加者の資格、入札者・入札金額、落札者・落札金額等)及び契約の内容(契約の相手方、契約金額等)を公表しなければならないものとしています。 この対象となる工事についても、発注見通しと同様、国、特殊法人等及び地方公共団体の行為を秘密にする必要がある場合や、予定価格が少額である場合は、対象から除外することとしています。 c)不正行為等に対する措置
|
| (4) 適正化指針の策定 全ての発注者に対して一律に義務付けることが困難な事項についても、入札及び契約の適正化について一定の方向性を示し、発注者に対し努力を促すための「適正化指針」を策定するとともに、その実効性を高めるため、措置の状況を調査し、その結果を公表します。さらに、調査結果に基づき特に必要がある場合には、国土交通大臣等から改善を要請することができることとしています。 a)適正化指針の閣議決定 国土交通大臣、総務大臣及び財務大臣は、関係省庁に協議し、適正化指針の閣議決定を求めます。また、国土交通大臣は、あらかじめ建設業の健全な発達を図る観点から、中央建設業審議会の意見を聴取することとしています。 b)適正化指針の内容 適正化指針においては、入札・契約適正化の基本となるべき事項にしたがって、次の事項を定めるものとしています。
国土交通大臣、総務大臣及び財務大臣は、毎年度、発注者による措置状況を把握・公表するとともに、特に必要があるときは改善の要請を行うものとしています。 |
(5) 国による情報の収集、提供等
|
|
(6) 施行 基本的に、平成13年4月以降に発注される公共工事に適用されます。 その他 ※ 適正化法の概要、骨子については、国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/)に掲載されています。 |
|